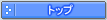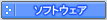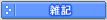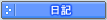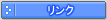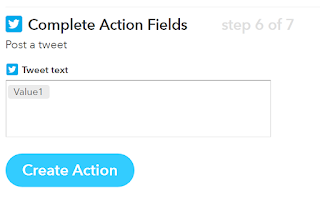友利奈緒 Advent Calendar 2016の8日目です。
月曜日。また一週間が始まる。
昨日は兄の見舞いに行ってきたが、何も進展はなかった。
能力の発現時期が過ぎれば、消え去った能力と引き替えに失われたものが戻ってきたりはしないかと期待した日々もあった。しかし医者の話では、そういうことはまず考えられないだろうとのことだった。組織による解決方法の研究も進んでいるようだが、それはあくまで能力の発現を止める方法であり、手遅れとなった人間のものではない。
脳に障害を受けて何十年と植物状態だった人間が、意識を取り戻す話を聞いたことがある。その人達も、脳細胞を何十年と掛けて再生させ帰ってきたのだ。きっと兄にもそれはできると思っているが、障害を受けた範囲がどの程度なのか、何十年というレベルで修復できるものなのか、今の医学では分からない。
わたしが生きている間に再び兄と言葉を交わせることができるのだろうか。そもそも能力の発現を止める研究もどのくらい進んでいるのか。仮に能力の発現を止める研究が完成した場合、組織はどうなるのか。今の兄の状況は維持されるのだろうか。
何も変わらない日々が続く中で、心配の種は尽きない。
「♪~」
鞄の中からメールの着信音が聞こえてくる。熊耳からの連絡だ。今日もまた能力者が現れたようだ。見つかった能力者を一人ずつ対処していく。これも変わらない日常の景色になってきた。終わりの無い日常。
いつも生徒会室に現れる少し前に連絡が来る。ここからなら、少し急げば間に合うだろう。足を速めつつ、いつも通りにメンバーへメールを送る。
生徒会室にはわたしと左手に高城、右手に黒羽さん。
ドアが開く。乙坂さんは遅刻と。
「ひっ」
メールからの時間ぴったり。黒羽さんが息を飲む。わたしもあまり慣れないが、服を着たままずぶ濡れにならないと能力者の位置が分からないという、これまた困った能力らしい。
能力者は何かのタイミングで自分の能力に気が付くわけだが、熊耳はどういうときに気が付いたのだろう。池にでも落ちたときに覚醒したのだろうか。プールでも発動するのだろうか。能力者が見つかったときに自ら水を被るのか、能力者を見つけるために常に水行をしているのか。もしかしたら、ものすごくドジで服を着たまま川にでも落ちてしまうのだろうか。しかし水が臭かったことは無いので水道水なのだろう。ふと、トイレで個室の上から水を掛けられる嫌な様子を思い浮かべる。本当にあちこち問題だらけだ。
四人が中央の地図に集まる。
「能力は・・・怠惰」
落ちた雫は自宅と学校の間ぐらいを滲ませた。
「ふぅ。まだ慣れないです」
黒羽さんが息をつく。
「しかたないです。わたしは怖がっているゆさりんも拝見できるので、どんどん怖がっていいと思いますよ」
「引くわー」
黒羽さんの芸能人としての活動、西森柚咲のファンクラブ会員でもある高城。彼女のことに関してはキモオタっぷりを発揮する。それは特殊能力ではなく、本物の能力は瞬間移動。しかしこれも一直線でしか移動できない不完全さだ。
生徒会で活動を始めた当初からのメンバー。その能力も何かと役に立っている。高城が居なければわたし一人で解決できない問題も多かっただろう。わたしの持つ能力では、暴力的な解決しかできない場面が多く、自然と周りの目も厳しくなった。そんな中、高城のサポートは大変ありがたい。
「怠惰の能力って、なんでしょう」
黒羽が同じ疑問を口にした。
「他人を怠惰にさせる能力か」
あまり使えなさそうな能力だ。一番この能力に影響されそうなメンバーの顔が浮かんだ。
「この調査は乙坂さんに担当させない方がいいでしょうね」
わたしの発言に他の二人は曖昧な笑顔を浮かべた。
「それでは乙坂さんはどうしましょう。待ちますか?」
「いつ来るか分からないし、放っておきましょう」
高城が申し訳なさそうに手を上げる。
「実はこのあと外せない用事がありまして」
ふむ。仕方が無い。まあ怠惰の能力だ。黒羽さんと二人で大丈夫だろう。
「では、二人で行きましょうか」
調査に出かけようとしたところでドアが開いた。
「わ、乙坂さん」
黒羽さんの声で遅刻者が到着した事が分かる。
「おせーよ」
「しょうがないだろ。こっちは大荷物抱えてるんだ」
「どうしたんですか?その荷物」
黒羽さんの脇から大きな段ボール箱を抱えて乙坂さんが部屋に入ってくる。
「カップラーメンが余っててな。小腹でも空いたときに食べてくれ」
「乙坂さんにしては気が利くじゃないっすか」
この活動は体力勝負なところが多い。この先いつまで活動が続くのか、どこまで資金が続くのか、いつしかこの生徒会室を最終拠点として活動を続けないといけない日が来るかもしれない。最悪ここに籠城という可能性もある。活動を続けるのに必要な資材はありがたい。
「そういえばメールが来てたが、出動か?」
「あたしと黒羽さんで行ってきます。男達は留守番な」
「おいおい、せっかく登校したのに」
いかにも不満そうな顔をする。
「生徒会の活動が無くても登校するのは当たり前だろ。それに今回の能力者を乙坂さんと会わせるわけにはいきません」
「なんだそれ。美人の能力者とかか」
ひくわー。ここの男達は本当にどうしようも無い。
「さ、行きましょう」
敢えて無視でいいだろう。黒羽さんを押して廊下へ出る。
「友利さん、調査ってわくわくしません?」
大きく手を振りながら歩く黒羽さんが聞いてきた。
少なくとも今はわくわくしていない。以前はどうだっただろうか。
「あの男の人から能力は伝えられますけど、実際にそれがどういう使われ方をしているのかとか、悪い使い方をしているのかなーとか、良い使い方をしているのかなーとか、良い使い方をしている人なら良い人かなーとか、いろいろ考えちゃうんです」
学生をしながら芸能活動もしている黒羽さんは、もしかしたらわたしよりもハードな生活を送っているかもしれない。こうして生徒会の活動も可能な限り付き合ってくれる。
わたしたちの活動は、能力者の保護だ。全ての能力者を成敗しているわけではない。良い人が良い使い方をしていたとしても、それを悪い使い方をしようと考える人も居る。
「みんながみんな、良い方向にしか使わなければいいんですがね」
黒羽さんだけでなく、わたしの希望でもある。
悪い使い方をしている能力者、悪い使われ方をしそうな能力については警告していかなくてはいけない。
「一昨日の茹でる能力も、あんなに美味しい料理ができるなんて、もったいないですよね」
「そうですねぇ。でも原理としては電子レンジと同じですから、使い方を間違えれば大惨事です」
そう、全ては使い方次第なのだ。
「お姉さんの能力だって色々な物は燃やせますが、良い使い方をしたおかげで一昨日は強力な火力が得られたわけですし」
美砂の能力、発火によって料理対決では審査員を唸らせる絶妙な火加減を実現できた。
もっとも、審査員はグルメレポート番組の経験から黒羽さんだったので、出来レースではあった。
「お姉ちゃんが褒められると嬉しいですね」
黒羽さんは自分のことのようにニコニコしていた。お姉さんはもうこの世の人ではない。どちらかというと黒羽さんとは反対の生き方をしていたので、どの程度交流があったのか分からないが、身内が評価されるのはやはり嬉しいものだろう。兄とのやり取りを思い出しながら、そんなことを考えた。
「♪~」
熊耳からの連絡だ。既に調査へ出発しているのに、さらに能力者が見つかったのか。今から戻るのは面倒だ。
「乙坂さんに頼むか」
「また能力者ですか? 多いですね」
「大忙しですよ」
メールを送ってカメラを構え直す。そろそろ目標の場所だ。
「猫ですね」
「猫ですね」
お互いに確認し合う。
住宅街の道の中央で太陽の光を浴びた茶トラ模様の猫が寝転がっている。起きてはいるようだ。
「気持ちよさそうですねー。でもこんなど真ん中にいたら車にひかれちゃいますよ」
黒羽さんが道の端にしゃがみ込み、手招きをする。ファインダー越しの猫はそれを一瞥しただけで、再び横になった。
「だめですね」
猫にはアイドルの価値は分からないらしい。耳を動かして近づいて来る黒羽さんの音を追っている。
黒羽さんは再び猫のそばでしゃがんで撫で始めた。
「動きたくないのかな」
撫でるだけでは飽き足らず、両腕を持って遊び始めたが猫は頑なに身体を起こそうとはしない。
「ずいぶん怠けものの猫さんですね」
黒羽さんの言葉にはっとする。これは怠惰の能力なのでは。
「もしかして、この猫が怠惰の能力者」
「猫さんは能力『者』なんでしょうか」
黒羽さんの疑問にわたしは確実な答えを持ち合わせていない。熊耳の能力もどのくらい確実なのか、そもそも動物も特殊能力を持ちうるのか、何もかも不明だ。
「それらしい人間がいるか探してみましょう」
わたしと黒羽さんが立ち上がり歩き出すと、それまでやる気の無かった猫が一緒に立ち上がり付いてきた。どうやらアイドルに撫でられてやる気が出たのか。高城の姿と重なる。
「おや、付いてくるんですか」
猫は黒羽さんの足元をぐるぐると回り出す。
「まるで高城みたいな猫ですね」
「あはは、急に元気が出ましたね」
「と、友利さん・・・」
心配そうに黒羽さんが見つめてくる。先程から見ていたのでわたしも状況が分かっているが、一応ツッコミを入れておこうか。
「黒羽さん、いつまでも遊んでないで調査を続行しますよ」
「うわーん、友利さんがいじめる」
黒羽さんにまとわりついていた猫は、先程までよりも速度を増している。みるみる加速していく猫はカメラの走査と同じぐらいの回転になっているのか、ファインダー越しには後ろ向きに歩いているかのように見え、そのうち停止しているような映像となっていた。
特殊能力というあまりにも非現実的な事象に普段から接していると、この猫のことでさえ冷静に見てしまう。
「この猫は怠惰の能力者ではなさそうですね」
「友利さん、落ち着いてないで助けてください」
「助けると言っても」
下手に黒羽さんが動けば高速な猫と衝突して無事では済まない。もちろんわたしも同じだ。この事態の前では、不可視の能力など役に立たない。
そんなことを考えているうちに、パチパチという音が聞こえて、やがてバチバチという激しい音と共に黒羽さんから放電が始まる。
「黒羽さん!」
手を伸ばそうと試みるが、大きな稲妻が伸びて来て思わず後ずさる。
いつしか黒羽さんの髪は大きく広がり、全身からスパークが伸びている。
「友利さん!」
助けを求める手を伸ばす度に放電が起きるので、それを避ける。このままでは近づくこともできない。
「黒羽さん、ちょっと待ってください。考えます」
「なんだこれは」
ちょうどそこへ乙坂さんが現れる。更なる新しい能力者も同じ方向にいたのだろうか。
「乙坂さ~ん、助けてください」
黒羽さんは乙坂さんへも助けを求めている。そうだ、あの能力があれば。
「乙坂さん、あの猫に乗り移ってどこかへ行ってください」
「はぁ?お前なんとかできないのかよ」
「やろうとしましたけど、無理なもんは無理なんだよ」
今来た乙坂さんでは状況が分からないだろう。ゆっくりと黒羽さんに近づいてみせる。
「つっ」
先程と同じように放電が伸びてきた。
「乙坂さ~ん」
黒羽さんが乙坂さんへ手を伸ばすと放電も飛んでいる。
「痛ぇ。わかった、わかったから」
乙坂さんの目が光ると共にぐったりと前に倒れ、黒羽さんとの距離が近づいたためスパークの餌食となっている。
乙坂さんが乗り移った猫は何周かした後、砲丸投げの球のように飛び出してきた。
こちらへ!
「ばかっ、よせっ」
あまりにも猫の速度は速く避けるのは難しい。このままではわたしも放電を食らってしまうし、感電によって筋肉が収縮し動けなくなるだろう。
猫はわたしの前でジャンプをして避けようとする。しかし猫のジャンプだ。高さがしれている。わたしを飛び越えるには至らず、飛び込んでくる。そうだ、感電によって筋肉が収縮するということは、あの動きならできるはず。
腰を落としてバレーボールのレシーブ体制を取る。位置を合わせたところでスパークがわたしの腕に当たり、重ねた手が猫の腹を押し上げる。
「うっ」
猫は若干低いうめき声と共に数メートル高く舞い上がり、再び地球の重力によって落ちてくる途中、電線に強力な電気を放出した。
ポンッという音と共に、あちこちの電柱から小さい煙が上がった。猫は塀の上に着地したかと思うと、放電に驚いたのか、音に驚いたのか、走り去ってしまった。
猫が離れたことにより、黒羽さんに帯電していた電気は無くなったようだ。
「乙坂さん、起きないですね」
黒羽さんが突いているが反応しない。高城なら突かれるために気を失ったふりをするかもしれないが、乙坂さんはそういうことはしなさそうだ。
乗り移っている間のダメージは本人の意識に送られるらしく、どのタイミングまで意識が猫にあったのか分からないが、この様子だと腹に両腕でフックを決めたところまでは意識があったのだろう。
「やむを得ないとは言え、少し悪いことをしました。仕方ないです。一度連れて帰って態勢を立て直しましょう」
二人で運ぶのは少し難しそうだ。高城は用事があると言っていたが、後から回収させることができるだろうか。携帯電話を取りだして電話を掛けてみる。
「あ、高じょ」
「今日はゆさりんのライブ予約電話を一番有利になる電話局前の公衆電話からチャレンジしたのですが、それでも戦いは激しく、やっと繋がったかと思ったところで辺り一帯に放電が走り、電話機からは火が噴き出し、二度と電話が繋がることはなかったのですよ!」
「引くな!」